『書くことが思いつかない人のための文章教室』を読んだ。「どう書けばいいかわからない」ときに、書く前の“考え方”を教えてくれる。
言葉を紡ぐ前に、何を見るか、どう感じるか。日常の視点を変えるヒントがあった。
感動や共感は、シンプルだった
私はずっと、感動や共感は特別な経験と難しい表現が必要だと思った。でも大切なのは、日常のシンプルな経験と、自分の思いを正確に言葉にすることだ。
- 感動には「描写力」が必要
- 共感には「状況」と「五感」が鍵になる
描写力を育てるには、「誰かに話すつもり」で見る。好奇心や、小さな違和感を大切にする。
そうした感覚が、自分だけの言葉をつくる土台になる。
共感は、「共に感じてもらうこと」。感情を押しつけるより、状況や匂い、手触り、空気感を伝える。
普通から使い慣れた言葉を使う。それが一番読みやすくて、伝わる文章だ。
カタカナ語や難しい言葉で悦に入っている人もいるけれど、私にはその言葉の奥が伝わってこないことがある。子供やお年寄りも分かる言葉で伝えたい。
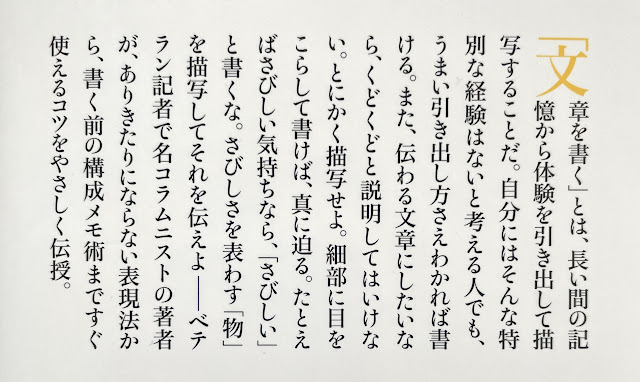 |
| 本の裏表紙に書いている言葉 |
感動は「ろ過」させて届ける
感動をそのまま流すと、伝わらない…どころか、書き手に熱がありすぎるため、読み手は冷める。
私の旦那さんは「ろ過」で例えた。
 |
| 私なりに解釈してみた |
時間をかけて自分の伝えたいことを考え、何回も書き直すことで、澄んだ一滴が絞り出される。
その一滴こそが「その人らしさ」となり、人の心を打つのだと思う。
心に残るのは、日常のこと
本に収録された短歌やエッセイは、派手な出来事はないのに読んでいると胸にじんわり残る。
観察と描写する力があれば、日常にも感動が宿る。その感動に触れた誰かが、自分の記憶や感覚と照らし合わせる。
「分かる」「違うけど面白い」そうした反応が、文章に深みをもたらすのかもな。
常に意識したい3つ
感動したことは、消えない
「記憶で試験勉強して覚えたより、感動で覚えることの方がやっぱり自分の身につく」
書くことは、思い出す作業
「具体的に描写しやすく、かつ書き進めやすい題材がいい。それにはやはり『思う』ことより『思い出す』ことだ」
作文は「あ」のもの
「人は感動を覚えると『ああ』とか『おお』とかの母音を発します。感動詞に『あ』が多いのもそういうことでしょうか」
これらは、自分だけの言葉をもたらすヒントになるらしい。感動、思い出、ひらめきは、誰にもマネできない独自の感性が生まれる。
実践して見えたこと
書く前のメモ、構成や編集のコツも紹介されていた。
ドリル形式の問いがあって、自分でも書いてみた。まとまりはなかったが、Chat GPTに添削してもらい、時間を置いた見直しで改善点が見えた。
この本を読む人にオススメしたいのは、ぜひドリルをやりながら読み進めてもらいたい。そうすることで、本への理解度が深まって、自分の文章の改善案も見えてくる。
まとめ
今の時代は何でも早く、効率を求められる。大事な想いまで誰の心にも残らず、ネットの海に埋もれてほしくない。
だから私は、すぐに忘れてしまいそうな「感じたこと」を、何度も思い返して言葉にしたい。
何度でも読み返したくなる一冊。






0 件のコメント:
コメントを投稿
Thanks for commenting! コメントありがとう!