古典は、他の言語を学ぶような難しい。それに、古いから読む価値なんてないと思った。
『枕草子』に出会ってから、いろんな古典作品(現代語)に触れた。今では、「人生の指南書」だ。
私の心に残る4作品の紹介と、私に与えた影響について。
枕草子
毒舌な赤裸々エッセイ…いや、実はラブレター?
 |
| kindle unlimitedで読める(2025年6月現在) |
香水はつけたてよりも、時間が経ってほのかに香るのがいい
誰も見てなくても、おしゃれをしたら気分がアガる
ある人の噂話をしていたら、本人がうしろにいたと知った時の気まずさ
時代も言葉も違うのに、人間の感情の根っこって変わってないのだと知って、胸がふるえた。清少納言と友達になって女子会したい。
枕草子は毒舌とユーモアで綴られる、いわば“宮廷エッセイ”。だけど、その背景にあるのは、主である定子への敬愛と、芯の強い女房・清少納言のまなざし。
もしかすると、定子への密やかなラブレターかもしれない。
清少納言は、嫌なことがあっても「上等な白い紙さえあれば、もう少し生きてもいい」と語った。実際に、辛い状況にあったとき、定子から紙をもらっている。
私はこのエピソードを、自分の「書くこと」と重ねてしまう。
話すのが苦手でも、書くことで気持ちを整えられる。私にとって「書く」は、心の中を整理し、救ってくれる時間だ。
そして、清少納言という人物にも惹かれた。
女性が漢字を使うこと、キャリアを追い求めることすら否定されていた時代に、堂々と教養と感性を武器にしていた彼女。聡明で勝ち気で、でも繊細。
私は彼女とは真逆のタイプだ。メソメソしてしまうとき、彼女の言葉を読むと、背中をパンっと叩かれるような気がする。
「もう、辛気臭いな!大丈夫よ!」って。
もし枕草子に出会っていなかったら、私はもっと他人に流されて生きていたかもしれない。
徒然草
ひねくれおじさんの旅日記
でもそこには、暇つぶしとは思えないほど鋭い気づきが詰まっている。
人はなぜかわずかな時間を見ない。その結果…。「寸陰惜しむ人」より。
過信しては足元をすくわれる。「もう大丈夫」な時こそ危ない?「高名の木登り」より。
なぜ人には怠け心があるのか。読んだあと、ぐうの音も出なかった。「弓を射る話」より。
どれも一見すると何気ないエピソード。でも、他人のふりを見て我がふり直しなさい、という教訓がさりげなく織り込まれていて、ドキッとさせられる。
兼好法師は、人が言いにくいことをズバッと書く。酔っ払いの醜態、人間の見栄や愚かさ。読んでいて小気味いいほど。
何よりも、徒然草から学んだのは“無常感”。私が悩んだときに徒然草を開くのはそのため。
「この人も悩んできたんだ」と思えるし、比べなくていいと教えてもらえる気がする。
現代は休息ですら「サボり」と言われる、人より何かができないだけで怒られ、逆にずば抜けても妬みの対象になる。SNSの断片的な情報で人を差別したりする風潮がある。
徒然草は「無常」という感覚で、立ち止まること、迷うことの大切さを教えてくれる。
もしこの本に出会っていなかったら、「なんで私だけこんなに悩むんだろう」って思い続けていたかもしれない。
でも昔の人も悩んで、寂しさを抱えていたと知ってから、「私はひとりじゃない」と思えるようになった。
論語
孤独に効く、自己啓発本?
 |
| kindle unlimitedで読める(2025年6月現在) |
今も使われている四字熟語の多くが、『論語』にルーツを持つと知ったときは驚いた。
でも、本当の衝撃はその後だった。
30代始め、私は人間関係に悩んだ。仲良くしていた友人が、ある人に差別的な発言をしたのだ。それを注意した瞬間、私は“仲間”から外された。寂しかった。でも、黙って受け流すことはできなかった。
そんなときに出会ったのが、論語のこの言葉だ。
子曰く、徳は孤ならず、必ず隣あり。
“まっすぐに生きていれば、ひとりにはならない。ちゃんと、見てくれる人がいる。”
その言葉に、胸の奥がじんわり熱くなった。論語の魅力は、単なる“名言集”ではないところ。
「どう生きたい?」と優しく問われているような気がする。
私は論語を「心の師」と思っている。“正しさ”を振りかざすのではなく、自分にも人にも誠実であろうとする。
お札になった福沢諭吉や渋沢栄一も読んだ論語。いろんな時代の、いろんな立場の人、国の人に影響を与え続ける。
もし私も論語に出会っていなかったら、あの時の孤独から抜け出せなかったと思う。それくらい、心を支えてくれる。
学問しぃや
「“学ぶ”って、生き方やで!」な教育書
 |
| kindle unlimitedで読める(2025年6月現在) |
「学ぶことの意味」が刺さる。読むたび、「肝に銘じます、諭吉先生!」とお辞儀したくなる。
知恵がないのが行き過ぎると、恥を知らんようになる。自分の無知ゆえに貧乏になって、経済的に追い込まれてるのに、反省もせんと、金持ちを恨んだり、ひどい時には集団で乱暴するていうこともある。
読んだ瞬間、胸がざわついた。
「うちの親やん。」
お金や知識、そして教育もなかったがゆえに、私の親は社会や他人を責めがちだった。両親は争いが絶えず、私たち子供はただその光景を見るしかできなかった。その末路は、一家離散。
この本と我が家の経験から、学ばなきゃいけないと痛感した。
点数や肩書きのためじゃない。よりよく生きる、“自分で幸せになるための”学び。私の旦那さんは、「学ぶと不満が減り、幸せを自分で作り出せる。」とよく言う。
その言葉の意味が、今では少しずつわかるようになってきた。
福沢諭吉も、論語を読んでいたそうだ。でもその内容をすべて鵜呑みにするのではなく、論語から自分で考え行動をした。まさに温故知新。
私もそうありたい。古典の教えをそのまま受け入れるのではなく、自分なりに考えながら、選びながら生きていく。
『学問しぃや』は、「勉強ができる」より、「考える力がある」ことの大切さを教えてくれる。
読んでから、私は不満が減った。そして少しずつ、「自分にとっての幸せ」を考えられるようになってきた。
以前、教育がないことで自分の可能性が狭まる、と私の体験談を書いた。(良いものを)選ぶ側ではなく、いつも(悪いことに)選ばれる側。
さいご
古典がこれだけ長く読み継がれてきたのは、時代を越えて、大事な教えがあるからだと思う。
私は、悩んだとき、つらいとき、勇気がほしいときに古典を開く。すると、「君はひとりじゃないよ」と、静かに語りかけてくれるような気がするのだ。
下記は、心に残る作品シリーズ。アニメのキャラたちの言葉に何度も救われてきたこと、自分と重なった部分を書いた。
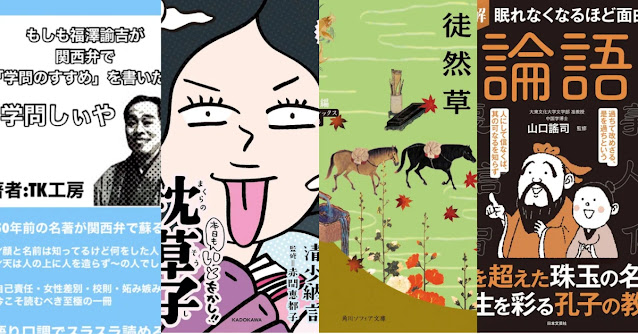


0 件のコメント:
コメントを投稿
Thanks for commenting! コメントありがとう!